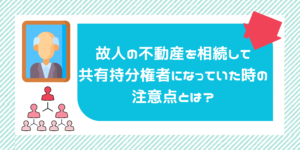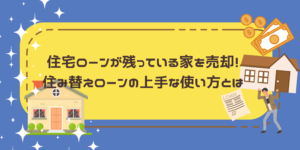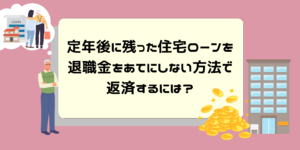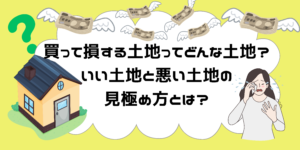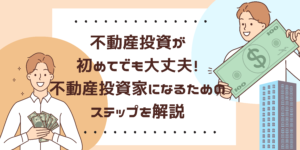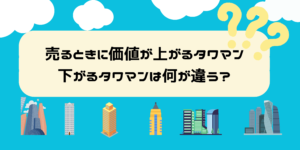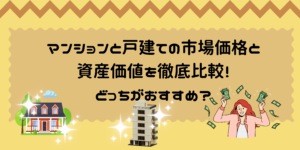「故人の所有していた不動産を相続して共有持分権者になっていたが、そのことを把握していなかった、知らなかった」ということがあります。
今回は相続で共有持分権者になっていた時の注意点をケースごとにわけて解説します。
ケースごとの解説

これから先、「えっ!?この土地、私にも権利があるの?」ということが誰に起こっても不思議ではありません。
不動産登記の義務化
このようなことが起こる理由は、「相続登記の申請が義務化」されたことにあります。
これまでは相続した不動産の登記が義務ではありませんでした。しかし、令和6年(2024年)4月1日から、相続登記の申請が義務化されることになりました。相続登記とは、「故人から相続した土地や建物について、所有権移転登記などをすることで不動産登記簿の名義を変更すること」です。「申請が義務化」とは、厳密には「登記」という作業を行うのは法務局であり、相続登記を行いたい人がすることは、その作業をお願いするための「申請」であることから、「申請が」の文言が入っています。実質的には「相続登記の義務化」と考えて問題ありません。
相続により不動産を取得した場合、取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行わなければなりません。令和6年4月1日より前に相続により不動産を取得している場合も対象となります。その場合は、令和9年3月31日(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)までに行わなければなりません。
正当な理由なく、相続登記の申請を行わない場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
「相続登記の申請の義務化」と聞いても、自分には関係ないと思うかもしれません。しかし、意外と他人事ではないかもしれません。
共有持分権者全員が知らないケース
「先祖が知らない土地を持っていた」ということが良くあります。特に、先祖が離れた土地で暮らしていた場合などに多くあることです。
相続登記が罰則付きの義務になると、「不動産の存在をしっかり伝えよう」「相続した不動産が他にもないかしっかり調べよう」という強制力が働きます。しかし、これまでは義務ではなく、そのような強制力がありませんでしたので、「あの不動産のことを伝え忘れた」「もし、あとから不動産が見つかったら、そのときに考えよう」となることもありました。その結果、相続人が誰もその不動産の存在を知らないままになってしまうことも多々あります。
相続人が相続した不動産の存在を知らなくても、不動産は残り続けます。しかし、そのことを相続人が知らなければ、その不動産を「誰が相続するのか」「相続人同士の持分をどうするのか」という相談をすることはありません。その場合は、法定相続分の割合で相続人が共有持分を有することになります。例えば、兄弟が3人で他に相続人がいない場合は、法定相続分はそれぞれ1/3の持分になります。誰も不動産の存在を知らないままの場合、このような相続がどこまでも続くので、次の世代で共有持分が細分化され、次の次の世代でさらに細分化されてしまい、ようやく不動産の存在が判明し、その世代の相続人が相続関係を整理しようと思った時には、その不動産の相続人(共有持分権者)が30人、一番低い持分割合は1/50ということになっている場合もあります。
このようにして、「えっ!?この土地、私にも権利があるの?」というようなことが起こります。不動産の存在が忘れられたのが昔になればなるほど、共有持分権者の数が増え続けていきます。相続は、場合によっては甥や姪など故人から少し離れた関係の人が対象になることもあります。そのようなことも相俟って、共有持分権者の数が多ければ多いほど、「故人の所有していた不動産を相続して共有持分権者になっていたことを把握していなかった」という事態の当事者になる可能性は高くなります。
では、このようなケースの当事者に自分がなっていた時、どのような対応をすれば良いでしょうか。どのようなことに注意すれば良いでしょうか。解説いたします。
所有不動産記録証明制度の活用

上記のケースは、相続登記の申請が義務化された背景です。このようなケースを放置していた結果、権利者(所有者)不明や権利者(共有持分権者)多数の不動産になります。そのような不動産は、管理する人がいないことが多く、周辺環境の悪化や空き家などの建物がある場合には倒壊の危険性があります。また、災害復興や再開発を行う時に、所有者の許可が必要になりますが、権利者が不明・多数では、許可を得ることができず、災害復興や再開発に支障が出ます。このような事態を打開するために、相続登記の申請が義務化されることになりました。
しかし、義務化により相続登記の申請を促そうとしても、相続人が、相続した不動産の存在を知らなければ、申請がされることはありません。ですが、そのような問題も想定されています。その問題の解決策となるのが「所有不動産記録証明制度」です。
所有不動産記録証明制度とは、特定の人物が名義人(所有者)となっている不動産の登録情報の一覧を発行してもらえる制度です。この制度を使えば、故人の所有していた不動産を把握することができ、知らない間に共有持分権者になっていないかどうかを調べることができます。相続登記の申請の義務を履行するにあたり、とても重要な制度です。
ただし、所有不動産記録証明制度は、相続登記の申請が義務化された令和6年4月1日の段階では開始されていません。令和8年4月までには始まる予定です。ご注意ください。
相続放棄には注意

上記のケースの場合、「今更、そんな不動産いらない」と共有持分を放棄したいと考える方も多くいます。その手段として、「相続放棄」を検討するかもしれませんが、このようなケースで相続放棄をすることは、ほとんどありません。
相続放棄をする場合、以下のような注意点があります。
①相続があったことを知った日から3か月以内に行う。
②一部分の相続放棄(ex.預金はもらうが、土地はいらない)はできない。
③既に相続財産の一部を相続している場合には相続放棄はできない。
上記のケースで、この3つの注意点をすべてクリアして、相続放棄ができる、相続放棄をする必要性があるというケースは極めて稀です。したがって、相続放棄は、あまり現実的ではありません。
遺産分割協議を行う

上記のケースの場合、一番の解決方法は、相続人同士が、新たに判明した故人が所有していた不動産についての話し合いを行い、共有持分権者の一人や特定の人物に共有持分を譲渡する、または、これからも全員で細分化された共有持分を持ち続けるなどを内容とした遺産分割協議をすることになります。
遺産分割協議を行う場合、以下のような注意点があります。
①遺産分割協議は、相続人(共有持分権者)全員で行う。
②相続人(共有持分権者)全員が一度に集まる必要はない。
不動産の相続人(共有持分権者)が多い場合、全員の氏名や住所を調べることに苦労する上、話し合いをするためには連絡をとる必要もあります。なかには、連絡がとれない人も出てくるかもしれません。しかし、そのような場合でも、氏名や住所が判明した人のみ、連絡がとれた人のみで、遺産分割協議をすることはできません。一部の人だけで遺産分割協議書を作成しても無効になりますのでご注意ください。
相続人申告登記の活用
(3)で解説したように、不動産の相続人(共有持分権者)が多い場合には、調べるだけでも時間が掛かります。しかし、その場合でも「不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内(令和6年4月1日より前に相続により不動産を取得した場合は令和9年3月31日まで)の申請義務が課せられた期間は迫ってきます。このようなときに利用する制度が、相続登記の申請の義務化と同時に開始された「相続人申告登記」です。
相続人申告登記は、不動産の相続人(共有持分権者)全員の調査や連絡に時間がかかる場合や遺産分割協議がまとまらない場合などに、不動産の所有者であった故人の相続人が、法務局に対して、①登記簿上の所有者について相続が開始したこと、②自分が相続人であることの2点を申し出ると、登記官が職権で申し出た相続人の住所と氏名を登記記録に登記する制度です。これを行うことで、相続登記の義務を履行したことになります。共有持分の割合を確定する必要もありません。ただし、相続人申告登記をしたあとで、遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割協議によって不動産を取得した相続人は、その日から3年以内に、相続登記を改めて行う必要があります。これは相続登記の追加的な義務になりますのでご注意ください。
<ケース2>で、Aが土地の存在を秘匿していたことが判明したあとも、土地を一人で占有し続け、話し合いに応じない場合には、BとCは相続回復請求権の行使をする余地があります。
相続回復請求権とは、相続人でないのに相続人のように振る舞う人(表見相続人)が相続財産を占有している場合に、本物の相続人が相続財産を返すように請求する権利です。
<ケース2>の場合、Aは相続人ではありますので、表見相続人には該当しません。しかし、このような場合でも、Aが土地を一人で占有し続けることで、他の相続人の共有持分が侵害されていますので、Aを相続回復請求権の相手方(請求される側)にすることができます。
なお、相続回復請求権は、相続権を侵害された事実を知ったときから5年が経過した場合、または、相続権の侵害を知らなくても相続開始から20年が経過した場合は時効により消滅します。相続回復請求権を行使できなくなるということです。ただし、土地の存在を秘匿して一人で占有している相続人は、他の相続人の共有持分を侵害していると認識していると思われます。その場合は、上述の期間を過ぎていても、相続回復請求権を行使して遺産を取り戻せる可能性があります。
相続土地国庫帰属制度の活用

上記のケースの場合、遺産分割協議((3)参照)をしたものの、不動産の相続人(共有持分権者)の誰一人として不動産を欲しがらず、押し付け合いになることも考えられます。そのような場合に活用したいのが「相続土地国庫帰属制度」です。
相続土地国庫帰属制度とは、相続等によって土地の所有権者や共有持分権者になった人が、その土地の所有権を国に渡す制度です。
相続土地国庫帰属制度の活用は一つの解決策ですが、以下のような注意点があります。
①不動産が共有の場合は、共有者全員で申請する必要がある。
②対象は土地のみで、建物は対象外となる。
③法務局による審査を受ける必要がある。
④審査手数料が土地一筆につき14000円かかる。
⑤申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する必要がある。
少し面倒な手続きかもしれません。おまけにお金もかかります。⑤については土地一筆につき原則20万円(例外あり)とされています。「いきなり共有持分がある」と言われた土地に「お金を払え」と言われれば、抵抗があるのは当然のことです。しかし、共有持分権者のままでは、固定資産税や管理費・維持費などで、もっと多くの費用が発生することも考えられます。将来的に発生する可能性のある費用も考慮した上で、相続土地国庫帰属制度の活用も検討してください。
共有持分権者の一部が知っているケース
1.は、不動産の存在が忘れられ、相続人(共有持分権者)全員が知らないまま放置していたケースです。しかし、相続人(共有持分権者)の一部が不動産の存在を知っていて、管理しているものの、他の相続人(共有持分権者)が不動産の存在を知らない、または、不動産の存在は知っていても、その不動産に自分が共有持分を有していることを知らないということもあります。以下のようなケースです。
Aは、自宅近くにある土地を駐車場として利用していました。この土地は祖父から父が譲り受け、父の死後は、Aが譲り受けて、管理や清掃などをしながら利用していました。相続登記の申請が義務化されたため、AはA名義の登記を行うために準備をしていたところ、名義が祖父のままになっており、父に譲る旨の祖父の遺言や、他の相続人との遺産分割協議がされていないことが判明しました。祖父の相続人は、父以外に父の弟と妹がいましたが、既に亡くなっており、父の弟には相続人B、父の妹には相続人Cがいます。
このような場合でも、祖父から父に「単独で相続させる」という遺言や遺産分割協議がない場合には、法定相続分の割合での相続となっており、Aの世代では、この土地についてA B Cがそれぞれ1/3ずつの共有持分権者となります。BとCが、この土地の存在を知らない、または土地の存在は知っていても、共有持分があることを知らないということは十分に考えられます。しかし、相続登記の申請の義務化を機に、AはBとCに相続登記の申請に協力するよう頼むことになります。そのタイミングで、BとCがその事実を知ることになります。
この場合、Aは「故人の所有していた不動産を相続して所有者になったと思っていたら共有持分権者だった」とい立場になります。一方でBとCは、「故人の所有していた不動産を相続して共有持分権者になっていたことを知らなかった」という立場です。この立場の違いはとても重要です。A B Cは、基本的には共有の不動産の権利を協力して処理する立場になりますが、BとCが自分に共有持分があることを主張した場合には、自分は所有者だと思っていたAは、突然、権利を主張してきたB Cと対立する立場になることもあります。
このようなケースでは、AやB Cは、どのような対応をすれば良いでしょうか。どのようなことに注意すれば良いでしょうか。解説いたします。
遺産分割協議を行う
1.(3)と同じことですが、こちらのケースの方が、遺産分割協議がより重要になります。
Aは、いくら自分が所有権者だと思っていたとしても、実際は共有持分権者であり、所有者になるためには、BとCの協力が必要不可欠です。遺産分割協議により、BとCの権利を譲ってもらうことが円満な解決のポイントになります。
一方のBとCにとっても、自分に共有持分があることを主張する場合には、遺産分割協議をどのようにまとめるかが重要なポイントになります。
遺産分割協議で、BとCの持分を無償でAに譲渡することもできますが、代償分割というAが単独で相続する代わりにBとCに現金を支払う、言い換えれば、BとCから共有持分を買い取る方法にすることもできます。
ただし、Aがこれまで、この土地を自分が所有者だと信じて、管理や清掃などに維持費を支出してきた場合には、BとCが自身の共有持分を主張するとなれば、AからこれまでAが単独で負担してきた費用を、共有持分に応じて負担するように求められる可能性があります。
上記のケースで遺産分割協議をする場合には、AはBとCに協力してもらう立場、BとCは自分にも共有持分があることを知らなかった土地をAに管理してもらっていた立場であることを、十分に留意した上で、遺産分割協議に臨むことが大切です。
相続回復請求権
BとCが自身の共有持分を主張して、Aに土地の明け渡しを要求してもAが応じない場合には、「相続回復請求権」を行使することができる可能性があります。
相続回復請求権とは、本来は、相続人でないのに相続人のように振る舞う人(表見相続人)が相続財産を占有している場合に、本物の相続人が相続財産を返すように請求する権利です。上記のケースのAは、相続人ではありますので、表見相続人には該当しませんが、このような場合でも、Aが土地を一人で占有し続けることで、B Cの共有持分が侵害されているのであれば、Aを相続回復請求権の相手方(請求される側)にすることができます。
相続回復請求権が行使されると、まずは当事者同士での話し合いとなりますが、それでも解決しない場合は、訴訟を起こすことになります。
時効取得の主張
これまで解説してきた(1)(2)は、どちらも相続に関することで、Aの立場からは不利なものでした。Aは自分が所有者だったと思っていましたが、実際には共有持分権者でしたので、相続の観点からは、同じく共有持分権者であったBとCから共有持分権者であることを理由とする請求をされた場合は、それに応じなくてはならない可能性があります。
しかし、これまで自分が所有者だと思って、管理や清掃を行い、その費用も負担していた場合は、突然、権利を主張してきた共有持分権者に対して、「この土地は私の土地だ」と言いたくなるのも当然のことかもしれません。
そのような場合に、Aが主張するべき制度が「時効取得」です。時効取得は、他人のものでも、自分のものとして一定期間持っていた場合には、自分のものにすることができる制度です。時効取得は相続とは関係のない制度になります。相続関係では対抗することが難しいAが、相続以外の制度でBとCに対抗するということです。
時効取得が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
①所有の意思をもって
②平穏かつ
③公然と
④他人の物を
⑤一定期間占有し続けること
問題になるのは①の「所有の意思を持って」です。一般的なケースでは、相続により不動産の共有持分権者になった場合は、他に共有持分権者がいることを知っており、「不動産の全てが自分のものではない」ということが分かっているので、所有の意思が認められず、何年経っても時効取得は認められないとされています。
しかし、上記のケースのAは、自分が所有者で、共有持分権者はいないと思っていました。
このような場合、Aが父からは「祖父からもらった土地だ」と何度も聞いていたなど、Aが自分は所有者だと強く信じるような客観的な事情がある場合は、時効取得が認められる可能性があります。時効取得の成立が認められるかどうかは、他の相続人や訴訟になる場合は裁判所の判断になり、ケースバイケースになります。固定資産税をAが負担していたか、Aは父が亡くなったとき既にこの土地を占有していたか、Aがこの土地の管理や清掃などを単独で行っていたか、BとCがこの土地についてどのような態度だったかなど、
総合的な事情を考慮して、「所有の意思」があったかどうかを判断することになります。
時効取得の要件を満たしたら、時効取得者が「時効取得します」と援用をすることになります。時効取得の成立をBとCが認めたら、A B Cが協力してA名義にするための相続登記を行うことになります。しかし、BとCが認めない可能性もあります。その場合は、訴訟になります。そこで、上記①の「所有の意思を持って」を含め、Aが時効取得の要件を満たしていると裁判所が判断すると、「A名義の相続登記をしろ」という判決が出されることになります。
Aにとっては、時効取得が認められれば、所有権を取得できますので、時効取得の要件を満たしていることをしっかりと証明する価値があります。反対に、BとCは、Aの時効取得が認められれば、自身の共有持分を失うことになりますので、Aの時効取得の成立を妨げなければなりません。時効取得の成立は、AとB Cの関係の大きなポイントになります。相続関係にばかり注目していると見落としがちなポイントになりますので、ご注意ください。
まとめ
以上、故人の所有していた不動産を相続して共有持分権者になっていた場合に、どのような対応をするか、どのようなことに注意するかを解説いたしました。2つのケースを挙げましたが、どちらのケースでも、最初に考えるべきことは、共有持分権者になっていた不動産をどうしたいのかということです。他の共有持分権者の権利も取得して自分のものにしたいのか、自身の共有持分だけを持ち続けたいのか、共有持分は不要なのか、それによって、取るべき対応や注意点が異なります。「共有持分はいらないと思っていたけど、やっぱり全部の権利が欲しい」と途中で気が変わっても、そこから変更をすることが難しいこともありますので、最初によく考えてください。